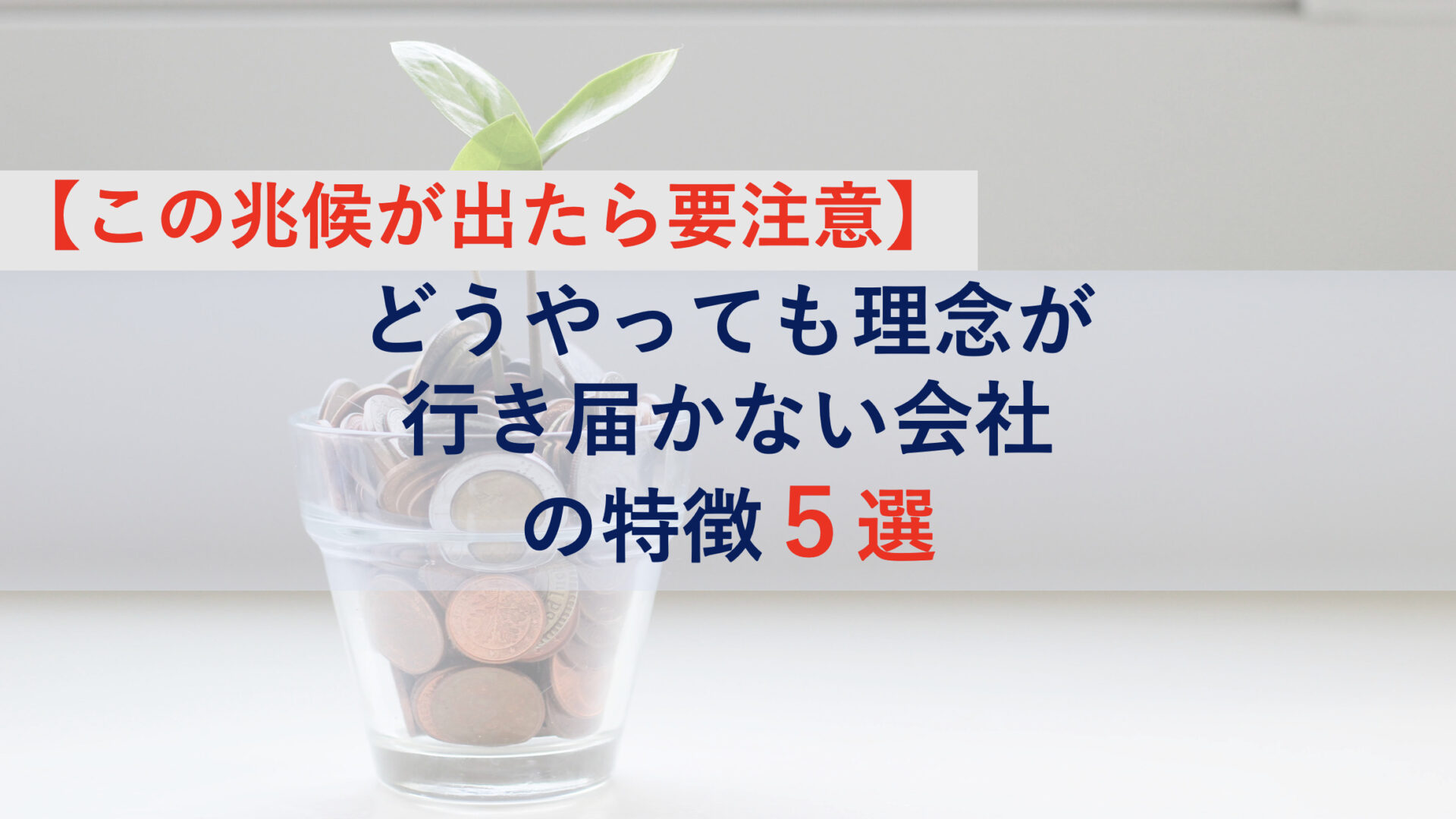目次
会社を作って、成長させる段階で、「企業理念を策定する」時が来ます。
立ち上げの時に作る場合もあれば、事業がある程度立ち上がった頃に作る場合もある。
作り方も様々で、社長が独断で決める場合もあれば、経営チームで話して決める、プロジェクトチームを立ち上げて決める、全社で話し合って決めるなど。
作るタイミングや作り方は手段なので、それぞれの環境に合わせた形でいい。
ただ、日頃から経営者やマネジメント層の方に話を聞くと「会社に一体感がない」という悩みを抱えていて、その根幹には「理念の浸透がうまくいかない」という組織課題を持っているところが多くあります。
今までいくつもの企業でこの組織課題と向き合ってきて感じるのは、実はいくら社長が頑張って発信をしても、そもそも浸透しないというポイントが5つあるということです。
どんなに素晴らしい花が咲く植物でも、そもそもの土壌がいい状態でないと育たないのと同じと考えると理由が分かるかもしれません。
私は17年間、スタートアップやベンチャーから上場企業まで様々な企業規模、成長フェーズの会社を見てきて、いずれの会社でもこの組織課題である「理念やパーパスの浸透」とそこから派生する問題に取り組んできました。
この記事ではどうやっても理念が行き届かない会社の特徴を5つ取り上げます。
それぞれの特徴を知ることで、組織課題を捉えることも、組織が崩壊するポイント、兆候も見えてくると思います。
企業理念とは
企業の「考え方」や「価値観」「創業者・経営者の思い」を言葉で表したもの。企業理念はその企業のあり方を示しているため、すべての企業活動の「根本的な考え方・信念」「経営を進める上での判断基準」となります。
理念を見つけ出す鍵となる問いは以下のようなものになります。
・会社が何のために存在しているのか?
・どこに向かって企業活動をしているのか?
・会社の強みは何か?
・日々どういうことを心がけているのか?
これらの問いへの自分たちなりの答えを考え続けると、そもそもの考え方に行き着くことができます。それが理念・パーパスになります。
なぜ理念・パーパスの浸透が必要なのか?

企業の会議では、よく「何をしたらいいのか?」が話されることが多くあります。
何をしたらいいのか?は仕組みや制度、施策に関する部分ですが、手段は数え切れないぐらいたくさんあります。
どの方法を行うのかの一つ一つは大きな要素ではなくとも、行うことの積み重ねが文化になっていき、それが根幹となる理念やパーパスに影響していきます。
つまり、根幹となる理念やパーパスへの深い理解や共感、浸透がないと、自分たちらしい文化は生まれず、仕組みや制度、施策は他の会社でもやっている「どこに行っても同じ状況」になっていきます。
ここでなければいけない理由がなければ、当然人はどんどん離れていき、組織が崩壊して、事業が立ち行かなくなっていきます。
その意味で、理念・パーパスの浸透は経営が取り組むべき重要な「組織課題」になります。
どうやっても理念が行き届かない会社の5つの特徴
今まで見てきた会社の中で、これではどうやっても理念は行き届かないだろうな、と感じたところで共通する5つの特徴があるので、ここで紹介します。
当てはまるものが一つでもあるなら、そこから亀裂が入り、組織が崩壊するかもしれないので、要注意が必要です。
①作って満足で、やがて無かったことになる
理念やパーパスを作るのはなかなかの労力がかかります。完成させることができれば、達成感を感じることでしょう。
全体の場で、社内外で作った理念やパーパスを発表する。きっと「自分たちもいいものを作れたよね」と言い合い、満足できることでしょう。
そして次のプロジェクトに取り組み出すという展開がほとんどでしょう。
せっかく努力して作った理念やパーパスでも、実は完成して発表した時点ではようやくスタートラインに立つ準備体操ができたぐらいの段階です。
その後の運用と継続が成否を分けるのですが、作って満足して、あとは誰もそれについて触れも語りもしないとなると、すぐに風化して忘れ去られて、無かったものになっていきます。
②キラキラ系、言葉寄せ集め系
理念やパーパスを作るためにワークショップなどを行うのですが、必ず出てくるのが「他社はどんな言葉を置いているのか」という他社事例ばかりが気になる人の存在です。
参考にする程度ならいいのですが、他社の素敵な理念やパーパスに大きく影響を受けて、そこから派生する「キラキラした」言葉にしたり、複数の企業の理念やパーパスから拝借して、単に良さそうな言葉を寄せ集めただけだったりすることもあります。
理念やパーパスは言葉として洗練させた方が伝わりやすくなりますが、そこに自分たちらしさや魂・イズムなどが込められていないものは、薄っぺらい印象を持たれます。
③その時の思いつきで言葉が練られていない
忙しくて十分に考える時間が持てない方に多いのが、「思いつきの言葉」で理念・パーパスを決めることです。
これまでの歴史や背景、今の状況の裏側にある思いなどを振り返ることなく、その時、その瞬間の思いつきで出た言葉であるなら、状況が少し変わると、また別の思いつきで言葉が出てきます。
やること、手段のレベルでコロコロ変わるのは、むしろ柔軟でいいのですが、根幹の思想、考え方が変わるのは、人の信頼・信用を失うことにも繋がります。
④社長の個人的な主張だけ
理念やパーパスの最初の起点は社長の個人的な思いになることが多いのですが、最初から最後まですべてそれだけで、社長の個人的な主張を言葉にまとめて、メンバー全員に「これに共感しろ!」と言ったところで、心に響くことはありません。
ただ理念やパーパスの成り立ちを確認すると、「結局、社長の個人的な思い、主張が表現されているだけですもんね」と現場の人から愚痴のような話を聞くことが意外と多くあります。
⑤社会的な意義がない
作られた理念やパーパスを見ると、「結局、自分たちの成功しか考えられていないんだな」と感じる自己中心的な言葉で埋め尽くされていることがあります。
人は一人では生きていけず、周りの人と協力する必要がありますが、企業も同じで、すべて自分たちだけで事業や組織が成立することはありません。
数ある会社の中で人がなぜそこで働くのか、を考えると、「自分のやっていることが社会に役立っている」や「これからやっていく方向が自分でもワクワクする」と感じられる会社を選び、そこで力を発揮したいと思うものです。
理念やパーパスをもう一度読み返してみましょう。そこに社会的な意義を感じる思いが、内容が込められているか。
まとめ
どうやっても理念が行き届かない会社の特徴として、今回5つ取り上げてみました。
いずれも会社内で「よく起きること」であり、もし経営陣にその実感がないのであれば、それ自体が「組織課題」になっていることになります。
取り上げた一つ一つを「こんなことは自分たちにはないよ」とバカにせずに、もう一度振り返ってみてみるといいかと思います。
ただ、自分たちの視点だけで客観的に最適な状態なのかを見極めることは難しいかと思います。